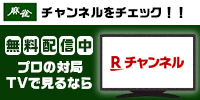上級/第64回『勝ちに向かう打法16』
2012年04月25日
1. 「手の伸ばし方の急所を知れ」
図A












 ドラ
ドラ
図Aの手で第一ツモが 。この瞬間、どんな最終手を思い浮かべることができるか。
。この瞬間、どんな最終手を思い浮かべることができるか。
それによって打ち手の力を測ることができる。
第一打で 。次にカン
。次にカン を引いて打
を引いて打 、
、 をツモって
をツモって を切る。
を切る。
これだけの手順で図Aの手は、タンピンの –
– 待ちの形になる。
待ちの形になる。
だが、もしあなたがこのような手順を思うとすれば、あまりにもストレート過ぎる。
手の伸びを考慮しない、融通性に欠ける人だとわかる。この手順だけで勝ち抜くことは難しい。
そのクセを直すには、実はたった1つのことに注意すればよいのである。
それは、第一ツモがマンズの なら、ピンズもソーズも同じ
なら、ピンズもソーズも同じ を生かしてみようと考える。
を生かしてみようと考える。
 、
、 をうまく使い切ろうとすることだ。マンズは
をうまく使い切ろうとすることだ。マンズは 、
、 とある。
とある。
ならば、ピンズもソーズも 、
、 と連携させて使おうと試みる。
と連携させて使おうと試みる。
と、今まで孤立牌に見えた がカンチャンに見え、
がカンチャンに見え、 も
も がくれば、複合させようという考えが生まれる。
がくれば、複合させようという考えが生まれる。
先の手順ではともに捨てられた 、
、 が逆に手の内で生かされ、図Bのような素晴らしい手に変化する。
が逆に手の内で生かされ、図Bのような素晴らしい手に変化する。
図B













この発想さえ身につければ、次々に大きな手役を完成させることが可能になってくるのである。
2.「知恵出づるの打法が勝ちへの第一歩」
「あのとき を切っていなければテンパイしていたのに・・・」
を切っていなければテンパイしていたのに・・・」
こくなボヤキをよく耳にする。
麻雀ではこの一牌の切り違いによって起きる明暗はずいぶんと大きい。
その場の戦局だけでなく、後々まで尾を引いてくるだけに始末に悪い。
図C












 ドラ
ドラ
図Cの手のところへ を引いてきたケース。
を引いてきたケース。
この人はピンズの受け入れを –
– だけと決めたようである。
だけと決めたようである。
好牌先打とばかり、いきなり 切りと出て図Dの構えに持っていったが、この一牌が問題だった。
切りと出て図Dの構えに持っていったが、この一牌が問題だった。
図D













これは初級者の人がよく犯すミスであるが、




 とある場合、
とある場合、 は粗末にできない牌なのである。
は粗末にできない牌なのである。
これを置いておくと、 ツモの
ツモの 切りというように待ちが広くなるのである。
切りというように待ちが広くなるのである。
葉隠の教えの中に「生附によりて、即座に知恵の一出づる人もあり、退いて枕をわりて、案じて出す人もあり」との一説がある。
天才的に才能を発揮する人もおれば、訓練によって才能を発揮する人もいるという意味であるが、
麻雀の場合は経験と訓練によって実力はついてくるものなのである。
一牌の切り違いで、せっかくの手を逃さぬよう考えた麻雀を打つことなのだ。
3.「顔をあげさせず打つ戦法に勝負のコツ」
図E












 ドラ
ドラ
図Eの手は南場2局、東家の手だが、この手、5,800点から倍満までの間の可能性を秘めた手である。
できればメンゼン手のタンピン三色手で完成させたいところであるが、そう思うようにいかないのが麻雀である。
うまくカン を引けるかどうかわからないし、首尾よく三色になるかどうかもわからないが、
を引けるかどうかわからないし、首尾よく三色になるかどうかもわからないが、
序盤である程度得点をたたき出していると、下手に食いを入れてリーチをかけられては・・・
と、消極打法に出てダラダラとメンゼンを続ける人が意外と多いが、これは間違った戦法である。
例えば、上家が を切り出してくるようなら、ここは積極的に食いを入れる。そしてアガる。
を切り出してくるようなら、ここは積極的に食いを入れる。そしてアガる。
実践での親はこう打ち、図Fのテンパイに取っている。
図F









 チー
チー


柳生新陰流の教えの中に「顔をあげさせずに打ちに打て」という教えがある。
一太刀打ったならば、それで相手をきることができようとできまいと、二の太刀、三の太刀と連続して打込み、相手に顔をあげさせるな。
これなら初太刀で勝負は決する、という教えである。
つまり、剣にかぎらず勝負ごとは、いったんつかんだ勝機はあくまでもこれを放さず、
積極的に攻めまくる、これが勝負に勝つコツでもある。
4.「我欲を抑えたリーチで常に平常心を保て」
図G












 ドラ
ドラ
図Gは東場1局、南家の手。三暗刻狙いで進めていたところへ、8巡目、 ツモときた。
ツモときた。
さて、この場面、あなたならどう打って、ここでの打法は2つに大別される。
一応、 を切り出すが、ヤミテンでまわし、
を切り出すが、ヤミテンでまわし、 か
か を引いての三暗刻狙いの人と、
を引いての三暗刻狙いの人と、 を切り出し即リーチに出るというタイプの人とだ。
を切り出し即リーチに出るというタイプの人とだ。
まずほとんどの人は東1局南家という立場を考え、後者の道を選ぶはずである。
南家は親落としの先兵でなければいけないのであるから、この戦法は間違いではない。
問題はリーチ後に1をもう一枚引いてきたときである。
ヤミなら図Hの形への変化を望めたわけだけに「しまった」と顔色を変える人がいるが、これは損だ。
図H













宮本武蔵の兵法の教えの1つに゛兵法の道において、心の持ちようは、常の心に替わる事なかれ。
常にも、兵法の時にも少しもかわらずして・・・゛という一節がある。
勝負のときでも平常心を保てという意味なのだが、まさにそうだ。
図Gの場面でリーチと行くからには、そのときすでに役への、“我欲”を抑えているのだから、
リーチ後何を引こうと悔やまないことである。
(文中敬称略)
カテゴリ:上級