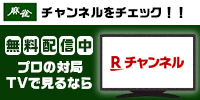プロ雀士インタビュー/第179回:プロ雀士インタビュー 前原 雄大 インタビュアー:紺野 真太郎
2018年03月08日
前原「まずは、A1昇級おめでとう」
紺野「・・ありがとうございます」

本来ならこちらから言うべきセリフを先に言われてしまった。これは前原の鳳凰位戦連覇のインタビューである。だが、そんな気遣いが前原らしい。
前原は見た目に似合わず相手のことを常に気遣う。このインタビューを行う場所を決めるにも
前原「何か食べたいものは?」
紺野「いえ、特に・・」
前原「そんなこと言わずに何かあるでしょう」
紺野「いえ、特に・・」
そんなやりとりが何度もあった。「ああ、昔から変わらないな・・」と思った。「じゃあ、あのパスタ屋さんに行こうか・・」そこは当時連盟新聞の編集会議後にみんなで行っていた店。まだあるだろうか・・
インタビューは夏目坂スタジオにて行うこととした。12時待ち合わせだったが、午前中の仕事が押して、スタジオ到着はギリギリになりそうだった。
{前原さんはもう来ているだろうな・・}
時間前であるが、そう感じていた。スタジオに着くとやはり前原はもう待っていた。
紺野「申し訳ありません」
前原「遅れたわけではないから・・でも紺野が時間までに来ないといよいよ事故かなと思ってしまうよ・・」
前原「昔、灘さんと待ち合わせした時に早めにいってもいつも灘さんが待っていらっしゃって、これはと、30分前に行ったら、それでもいらっしゃるんだよ。それじゃあと40分前に行ったら、ようやく先に着くことが出来た。ああ、灘さんは30分前にいらっしゃるのだと。それからは最低30分前にを心掛けてるよ。」
紺野「そうですね。自分もそういうタイプですけど、やはり何かがあったときに30分あればと思うので。」
前原「そういうことなんだろうね。」

前原「これは、あまり拾われてなかったんだけど・・」
紺野「はい。」
前原「最終戦の南2局、内川の親でリーチを受けて・・瀬戸君が を押して・・」
を押して・・」
紺野「この場面ですね」


(瀬戸熊は西単騎の七対子テンパイ)
前原「 を打つのは簡単なんだよ。でもプライドがそうさせなかった。」
を打つのは簡単なんだよ。でもプライドがそうさせなかった。」
紺野「プライドですか・・」
前原「損得だけ考えたら打った方が得なんだろうけどね。プロとして・・というよりも麻雀打ちとしてのプライドがそうさせなかった。」
紺野「残り3局で親の内川からリーチ。それに対して当面の相手ではない瀬戸熊さんが押す。リーチにこない瀬戸熊さんならば、親の現物待ちの可能性が十分。確かに局消化を考えても、 で切り抜けたくなる場面ですね。」
で切り抜けたくなる場面ですね。」
前原「でも、私はそれをやっては勝負で勝ったとは言えない気がするんだ。」
紺野「では、力が足りずに で放銃してしまうのは?」
で放銃してしまうのは?」
前原「それは話が別さ。待ちが読み筋にあるのに打つのは勝負に反することかなと思う。変則手だし、 だけは打つまいと思ってたよ。」
だけは打つまいと思ってたよ。」
紺野「試合に勝って勝負に負けるみたいな・・。 を打つ方が簡単ですけどね。」
を打つ方が簡単ですけどね。」
前原「そう。簡単なんだよ。簡単だからこそ、チームガラクタはそれをやらない。確かに方法論としてはアリかも知れないけれど、そこに麻雀の本質は無いように思う。 が読めたとしてそれを打つのは私では無いから。だから、私なんかは麻雀プロではなくて麻雀打ちなんだろうね・・」
が読めたとしてそれを打つのは私では無いから。だから、私なんかは麻雀プロではなくて麻雀打ちなんだろうね・・」
麻雀打ちという言葉はすっかり聞かなくなった様な気がするが、連盟の先輩方を見ているとそういう言葉を感じずにはいられない。
13回戦東1局の話題に・・
前原「それにしてもあれはまいったな・・」
紺野「あの ですか。」
ですか。」
前原「そう。指で触った瞬間に だなって。そう思って切ってしまった。ロンと言われた時は何が何だかよくわからなかった。」
だなって。そう思って切ってしまった。ロンと言われた時は何が何だかよくわからなかった。」
紺野「上に乗せて確認してないんですか?」
前原「あれは視聴者が見やすいようにするのであって、目線は河や相手の表情だから。誤ポンもして、本当に対局者に申し訳ないと思っているけど、そういうのが加齢ということなんだろうね。」
前原「鳳凰位にしてもお借りしているという意識が強くてね。テーブルゲームで60過ぎの人間がトップなんてあり得ないから。」
紺野「新陳代謝の無い世界は滅びる。前原さんがよく仰る言葉ですね。」
鳳凰戦が始まる前、いや、正確に言うと去年鳳凰位に復冠したときから、前原は「連覇は無いよ」と言っていた。勿論、自信が無いとか、手を抜くとかそういう意味ではなく、還暦を過ぎた自分がトップでいいのだろうかという葛藤にも似た思いからである。
前原「2日目が終わった後、黒木君に誘われて伊集院静さんの所に行ったの。2次会にも伊集院さんに誘われて行ったんだけど、伊集院さんに「どうなんだ」と聞かれ、引き際も考えてますよと、勝つ意義も見当たらないように感じてと答えたんだ。そうしたら伊集院さんに「高い壁であれ」と言われ、また会長にも同じような事を言われてね。」
紺野「高い壁ですか・・(高すぎやろ・・)」
前原「それがモチベーションになったかな・・」
紺野「そんな中、鳳凰戦に向けての準備はどうしていたのですか?」
前原「大体2か月くらい前から、公式ルールは勿論だけど、三人麻雀を打ち込んでいったよ。」
紺野「サンマですか・・」
前原「サンマの方が流れがわかりやすいから。我慢すべきとこは徹底して我慢して、攻める時にも徹底して攻めるみたいな。」
紺野「どれくらいの頻度で打ちこんでいたのですか?」
前原「暇さえあれば」
紺野「普段は大体週1、2のペースで公式ルールのセットとかをやっていたじゃないですか。それが通常時だとすると、調整時は・・」
前原「暇さえあれば」
紺野「セットしてサンマしてみたいな・・」
前原「そうだね」
最近の若手は打荘数が減少傾向にあると思う。情報が溢れているので収集しやすく、技が覚えやすいからであろうか。
前原「今回のメンバーがって事じゃないけど、みんなうまいんだよね。技というか・・」
紺野「そうですね。麻雀を勝負ではなく、ゲームとして捉えているというか・・」
前原「でも技は技でしかないから。技で勝負は決まらないって。さっきのプライドの話にも通じるんだけど、例えばね、色々な映像対局を見ているけど、解説がここは前原打ち(放銃)に行きますかね。みたいな事を言ってるの。そうした方が得かも知れないけど、こっちはその局12,000放銃も覚悟で前に出てるんだよね。全然捉え方が違うんだなと。やっぱ解説は難しいんだなと。」
紺野「前原さんの戦い方はある意味異端に思われています。」
前原「そうなんだろうね。ある時期「ゲーム」という言葉をよく使っていたけども、何か違うような気がして・・」
紺野「前原さんにゲームは似合いません。似合うのは勝負です。」
前原「そうなんだろうね(笑)だから、やっぱり麻雀プロではなく麻雀打ちなんだろうと」
パソコンを前にしても殆どいじらずに話込んでしまう。麻雀の話なのだけど、牌姿は全然出てこない。でも、いつも前原と話す時はこんな感じである。録音はしているが、インタビューしている感覚はとうに忘れている。
紺野「せっかくパソコンを用意してもらったのに、1局しか見ていないので、もう少しいいですか。最終戦オーラスなんですが・・」
オーラス、最終手番で前原の長考が入った。見たことがないほどの長考。放銃すれば負け。しなくても次にツモられたら、やっぱり負け。見ていたこっちからは「 が打たれてしまうのではないか。」とも思わせた場面。
が打たれてしまうのではないか。」とも思わせた場面。
紺野「 を打たなかったこともそうなんですが、あれは多分、前原さんが、全ての麻雀において一番時間を掛けた一打だったのではないかと思いまして。」
を打たなかったこともそうなんですが、あれは多分、前原さんが、全ての麻雀において一番時間を掛けた一打だったのではないかと思いまして。」
前原「そうみたいだね。」

前原「この に間があったんだよね。だからマンズのメンツがあるのかと。」
に間があったんだよね。だからマンズのメンツがあるのかと。」

HIRO柴田の8巡目手出しの を指している。前原はこの局ノーテンと手を伏せれば連覇。一方の柴田は満貫直撃か跳満ツモで悲願の鳳凰位となる。
を指している。前原はこの局ノーテンと手を伏せれば連覇。一方の柴田は満貫直撃か跳満ツモで悲願の鳳凰位となる。
前原「なぜ で考えるのかなと。
で考えるのかなと。

 ってあるのかな。マンズの一通のカン
ってあるのかな。マンズの一通のカン もあるのかなと。だから、9巡目の
もあるのかなと。だから、9巡目の が打てなかったんだ。」
が打てなかったんだ。」
紺野「ではここから実質的にはオリに向かったと。」
前原「そう。ここからオリに向かったね。」
紺野「そして、11巡目に柴田からリーチが入るのですが、この時は柴田の手をどのように考えていましたか?」
前原「ドラ切りリーチだけど、ドラ頭の一通か三色だと思っていたよ。」
紺野「七対子は考えなかったんですか?」
前原「やっぱり で考えたってことはメンツ手なんだよ。」
で考えたってことはメンツ手なんだよ。」
紺野「七対子は消せたと?」
前原「いや。完全に消せたわけではないけど、メンツ手よりは薄いかと。」
リーチを受けた段階で安全牌は5枚。流局までには2枚足りない。途中 を引いてあと1枚。しかし、その1枚が引けぬまま最後のツモ・・
を引いてあと1枚。しかし、その1枚が引けぬまま最後のツモ・・
前原「これは勘違いしてる人もいたみたいだけど、仮に が4枚見えていても
が4枚見えていても は打たないんだよ。一通か三色と思っているから。元々
は打たないんだよ。一通か三色と思っているから。元々 でやめてるぐらいだから。123の三色は無いから、正直
でやめてるぐらいだから。123の三色は無いから、正直 か
か の選択だったよ。」
の選択だったよ。」
紺野「そこで があったので
があったので の選択になったと・・」
の選択になったと・・」
前原「そういうことだね。」
そろそろ時間となり・・
前原「これは言っておきたいことなんだけど・・まだ譲る気はないから」
紺野「奪い取れと」
前原「そう。奪い取ってくれ。みんな本気で取り組んで奪い取って欲しいよ。去年、瀬戸君が観戦記で書いていたけど、前原さんはヒールであって欲しいって。でもヒールって強くないとだめだからね。」
紺野「前原さんにはヒールが似合っていると思いますよ。風体的にも・・(笑)」
前原「風体はオマエには言われたくないわ(笑)」
録音しつつの3時間もあっというまに過ぎた。正直書ける話、書けない話は半々といったところであった。
前原「じゃあパスタ食べに行こうか。」
紺野「ごちそうになります。」
17年ぶりに訪れたパスタ屋は今も当時のまま営業していた。不思議なことにメニューを見ると、何を好んで注文していたのかすぐに記憶が蘇る。しかし、ただ1つ残念なのは伝える為の写真を撮ることを完全に忘れていたことであった・・

カテゴリ:プロ雀士インタビュー