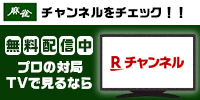第244回:プロ雀士インタビュー 二階堂瑠美 インタビュアー:長村大
2022年07月25日
「お疲れさまです」
そう言って二階堂瑠美がおれの前に座る。
こんなことが昔はよくあったような、でも初対面のような、不思議な感じがする。昨年4月にプロ連盟に入ってから、たまに覚える感覚だ。
ほんとうの初対面は、もう二十年以上前になる。その時のことはまったく憶えていないが、おそらく先にプロになっていた二階堂亜樹の姉、という触れ込みだったはずだ。
その後おれがプロ業界を離れてからは、2~3度セット麻雀を打ったくらいだろうか。もちろんおれの側からは活躍を耳にしてはいたが、なんというか、もう別の世界の住人であるような感覚であった。
今回は、その瑠美のインタビューを請け負った。
こういうの、「エモい」って言うのかな。年寄りなのでニュアンスがわからない。
長村「まずはプロクイーンに続きグランプリMAX優勝、おめでとうございます」
瑠美「ありがとうございます!」
蛇足ではあるが、なぜ今頃こんな話を、と思っている読者様にお詫び申し上げなければならない。単純におれが原稿サボっていたからです。すみません。
長村「グランプリMAXは、やっぱりラス前の1,300・2,600が大きかったよね。みんな言ってるけど」
瑠美「そうですねー、でも私的にはその前のベスト8が大きいかな。決勝で戦った渡辺史哉くんと、寿人さんと競りになって。オーラス寿人さんから7,700直撃して勝ち上がったんだけど、内容も良かったし、『寿人に勝った』っていうことでなんとなく運気も上昇してるような(笑)」
長村「決勝も渡辺くん、良かったよね」
瑠美「しっかりしていると思います。でも決勝はちょっとバランス崩してたかも。少し押しすぎなんじゃないかな、とは思いました」
長村「で、ラス前のアガリがあって、けっこう有利になってのオーラス」
瑠美「実はラス前より、オーラスのほうが気になってるんですよね。まあまあアガれそうな配牌だったけど、優勝争いの紺野(真太郎)さんのダブ が1枚だけあって。迷ったけれど、結局第一打に切ったんですよ」
が1枚だけあって。迷ったけれど、結局第一打に切ったんですよ」
長村「なるほど」
瑠美「もし鳴かれてダブ ドラドラ、とかツモられたら負けちゃうから、けっこう長考した気がしてたんですが、見返してみるとそんなに時間つかったわけでもなくて。だからどう、ということでもないですが、ちょっと不思議でした」
ドラドラ、とかツモられたら負けちゃうから、けっこう長考した気がしてたんですが、見返してみるとそんなに時間つかったわけでもなくて。だからどう、ということでもないですが、ちょっと不思議でした」
長村「時間て不思議だよね、その時々で伸び縮みする」
瑠美「そうなんですよね! 流局するまでめちゃめちゃ長く感じるし!」
長村「ちなみに、勝ってから反省とかってある?」
瑠美「プロクイーン勝ったときは、そんなになかったんですよ。そんなにツイてたわけじゃなくて、厳しいところから勝てたし。だけどグランプリはずっとツイてて、そうなると逆にダメなところが目についちゃう。オーラスの第一打 もいまだに『よかったの?』って思ってるし」
もいまだに『よかったの?』って思ってるし」

長村「それはなんとなくわかる気がする。アガれそうな手をもらってアガれないと、『うまくやればアガれたのでは?』って思っちゃうもんね」
瑠美「そうそう」
長村「決勝はマークしてた相手とかっていたの?」
瑠美「マークとかじゃないけど、渡辺くんは勢いがあるなって」
長村「若いもんねえ」
瑠美「25才ですってよ!(笑)」
長村「我々にもそんな時代がありましたかねえ」
我々にも、そんな時代があった。そしていまだ、そんな感覚で生きている、少なくともおれは。でもたぶん、それはおれだけじゃない。
長村「若手で、気になってる選手とかっている?」
瑠美「やっぱり今言った渡辺くんと、あとは岡崎(涼太)!」
長村「岡崎ね(笑)」
瑠美「今の若い選手って、やっぱりみんな真面目で、それは良いことだとは思うけど。岡崎はヤバいよね、おもしろい(笑)」
なにがヤバいのか、おもしろいのかは、ここでは触れないでおこう。
このあたりで、もしかして触れられたくない、かもしれない話題を振ってみた。
長村「さて、今年はMリーグもあったね」
瑠美「ありましたねえ」
特に機嫌を損ねた風ではない、大丈夫か。まあ大丈夫なのはわかって聞いているのだけれど。
長村「ほら、今年は結果もいまいちだったし、なんならけっこう叩かれちゃったりもしたじゃない。そういうの、気にするほう?」
瑠美「全然! 叩かれたりはまったく気にならない! だってさ、叩いてる人たちの中に、私より麻雀に時間使ったり、考えたりしてる人なんていないもん」
もちろん「麻雀を打っている」時間だけにフォーカスすれば、瑠美より多い人間はたくさんいるだろう。だが、麻雀に捧げている時間、となれば話は別だ。
瑠美「だから、叩かれたりとかそういうのはいいんだけど。ただ、今年はあまり楽しんでやれなかったかなって」
長村「そうなの? 傍からはそんな風には見えなかったけどね」
瑠美「なんというか、チーム戦というものに慣れてないじゃないですか、やっぱり。自分の負けがチームの、全員の負けになっちゃう」
長村「チームメイトだけじゃなくて、会社やスタッフさんもいるもんね」
瑠美「そうなんですよね。それで、自分の選択じゃなくて、無難な選択に流れちゃってたかな」
長村「なるほどね」
瑠美「やっぱりプレッシャーもあって。外で見てたのと、中にいるのでは全然違う。もちろんそんな泣き言言ってられないけど、例えば他にもっと若手を獲ってもよかったのに、とか思ったりもするし。だから、来季以降はもっと楽しんで、自分のやりたいようにやろうかと思います! それがあるから、自分を選んでくれたんだしね」
そういえばキャッチフレーズは、天衣無縫、であった。
長村「プロ連盟に入って、もう20年くらい?」
瑠美「23年、かな?」
長村「おれは昔のことはわかるけど、途中がゴッソリ抜けてて。でも麻雀の世界も変わったよねえ」
瑠美「昔と全然違いますもんね」
長村「麻雀ファンの人も増えてくれたしね。昔の自分に言いたいことってある?」
瑠美「『ネットゲームに課金するな!』かな(笑)。データだから! なんにも残らないから!(笑)」
長村「そんなに?(笑)」
瑠美「酷いもんですね(笑)」
長村「でもさ、まああんまりこういうこと言うのもなんだけど。正直言えば、おれは二階堂姉妹は、なんというか、こんなにバリバリの『麻雀打ち』になっていくとは思ってなかったのね。どちらかというとほら、マスコットというかアイドル的な……」
言いづらいことなので歯切れが悪い。だが、瑠美はしっかりと答えてくれた。
瑠美「それはわかります。たしかに連盟に入ったころは、リーグ戦も義務みたいな感じに思ってたし、なにもわからないままにテレビに出て安藤さん(故・安藤満プロ)と麻雀打たせてもらったり。ありがたかったけど、正直しんどい部分もありました」
長村「アイドル的な役割を求められたりもあるだろうしね」
瑠美「そうですね、でも私たち(姉妹)はアイドルになる気は全然なかったですけどね(笑)。やっぱり連盟員として、自分の価値を高めていきたい、というのはありました。麻雀のプロなので」
もちろん──そうでなければ、一流のプレイヤーにはなれない。だから当たり前のことではあるのだが、改めて彼女の芯の強さを見た気がした。
長村「麻雀プロとして、自分の『麻雀観』みたいなものってある?」
瑠美「セオリーは当たり前にあって、その向こう側というか、そこからひと手間ふた手間かけて、とは思ってます。『ツイてないからラス』じゃ味気ないじゃないですか。自分が一番手じゃなくても、一番手に楽をさせないように、なにかできることはあると思うし」
長村「『一番手』というのは、いわゆる『ツイてる』って意味?」
瑠美「そうですね、そのへんはデジタルなんちゃらの長村さんとは意見が合わないとは思いますけど(笑)」
「デジタルの申し子」です。46才ですけど。
瑠美「考え方ややり方はいろいろあると思いますけど、私にとっては『麻雀のことをもっと知りたい』のが、麻雀プロとして在り続ける理由なんですよね。やればやるほど、できないことの多さに気付いていくし。だから麻雀はおもしろいんですけど」
麻雀プロとして、第一線で長く戦い続ける。そのためには技術はもちろんだが、それ以外にも必要なことがたくさんある。当然ファンあっての存在でもある。
だが、やはりいちばん大切なのは麻雀なのだ。麻雀としっかり向き合わずして、なんのプロであろうか。
当代一の人気プロが、そう言っている。
ちょっとSNSでチヤホヤされたり、それは嬉しいかもしれないけれど、そんなのは麻雀じゃない、全然。おれも足元を見つめ直さなければいけないな、と思った。いや、思わされた、と言うべきかもしれない。

~~エピローグ~~
インタビューを行った新宿から、彼女は車で帰るという。
長村「なに乗ってるの?」
何気なく聞いてみた。
瑠美「〇〇(車名)です」
長村「え、それまだ現行車あったっけ?」
瑠美「いやもうないんですよー。でも好きで、わざわざ古いやつを取り寄せて買ったんです!」
なんだか、意外だった。
かつて──語弊を恐れずに言えば──なんだかフワフワとした「麻雀を打てる女性」だった彼女が、今や一流の打ち手となり、硬派なクルマ選びをしている。
それが20年という月日だ、と言われればそうなのだが、同時にそれはおれが体験しなかった20年でもある。
やっていた者とやらなかった者。そこには必ず差があるはずだ。そしてその差を──これからおれは埋めていくことができるだろうか。
そんなことを思いつつ、駐車場に消える彼女を見送った。

カテゴリ:プロ雀士インタビュー