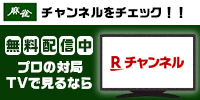戦術の系譜16 内川 幸太郎
2021年02月22日
この戦術の系譜コーナーも僕で6人目。
色々な方がそれぞれの視点で戦術を書いていますが、改めて麻雀は人それぞれだなと思います。
もちろん基本的な牌効率や打点効率の部分は強者ならば皆共通ですが、それプラスアルファの所は千差万別の戦い方があります。
麻雀を上達するためには知識(引き出し)を増やすことも大切ですが、その知識をどの場面で使うのか?という事がもっとも大切だと思います(そのための実践量も大切)
例えばこの場面。
A

状況はまだ東場。
わずか4巡目でテンパイできました。
ドラ1カンチャン役無しは即リーチ!
現代麻雀はこれがセオリー!みたいな説明、見た事ないですか?
いや、合っています、使い方さえ間違えなければ。
もう少し丁寧に説明すれば、
 のカンチャンはリャンメン変化が
のカンチャンはリャンメン変化が の一種に対してアガリは
の一種に対してアガリは の一種。
の一種。
2回に1回は好形変化よりもダイレクトにアガリがあるので、変化を待たずに即リーチする方が良いというものです。
もちろんリーチ後はロンアガリも出来ますし相手に制限も与えられます。
ただ、もう一度自身の手を眺めてみて、今置かれている状況を考えてみてください。
この手にはタンヤオがすぐ見えますし、イーペーコーも2手で見えます。
4巡目という素晴らしく早い巡目も嬉しい限りです。
先手を重視して一発や裏ドラで打点をカバーするのも良いですが、自身の手牌の伸び代を加味する事とその猶予(巡目)を見誤らずにいる事が大切になります。
B

 と
と が1枚違うこの牌姿。
が1枚違うこの牌姿。
こちらは先程あげた伸び代が無い形。
これは即リーチの引き出しを使ってあげましょうか。
ただ、 や
や が重なった時のシャンポンリーチの優位さは、こちらの牌姿の方がいいなという認識は必要です。
が重なった時のシャンポンリーチの優位さは、こちらの牌姿の方がいいなという認識は必要です。
常に伸び代を考え、その上で知っている知識(今回でいうと役無しドラ1カンチャンは即リーチというもの)を実践していく事が大切です。
もちろんオーラスアガリトップなどの条件下では、A、Bともにリーチ優位になる事が多いことは追加しておきます。
そもそもですが、上記2点の牌姿AとBでは、前提が大きく違います。
Aはこの半荘の決まり手(満貫、跳満)になりうる形で、Bはその局を制するレベルの手です。
細かいアガリと繊細な守備で半荘を制する事もたまにありますが、トップ意識が高いゲームではかなり展開に恵まれないとそれはなかなか苦難な道です。
やはり決まり手をくり出し、展開をも味方につけるような一局が必要になってきます。
実戦では4巡目ヤミテンからの次巡ツモ で打
で打 。アガリ逃しになる
。アガリ逃しになる 引きもピンフとタンヤオが付くなら問題無しの構えをとりました。
引きもピンフとタンヤオが付くなら問題無しの構えをとりました。
マンズが雀頭になる 引きで7巡目にテンパイしてリーチといき、見事10巡目で
引きで7巡目にテンパイしてリーチといき、見事10巡目で 引きアガリの満貫となり、この半荘を優位に進めることに成功出来ました。
引きアガリの満貫となり、この半荘を優位に進めることに成功出来ました。

このように僕の普段意識している戦術が、皆さんの麻雀ライフでのひとつの引き出しになれば良いなと思います。
麻雀の基本原理は、加点を増やし失点を減らす。
戦術の多くは攻撃面と守備面に分かれますが、一局だけをみたものと一半荘、またはその日一日をみたものもあります。
これから何回かに渡り書いていきますので、僕の知識を少しずつ楽しんでいただけると幸いです。
カテゴリ:戦術の系譜